この記事は本を紹介したところから始まる進化論と人類についての講義である。
まず時間を用意することを薦める。
講義を始めるにあたって
進化の話をしよう。別にポケモンの流れに乗っかろうというわけではない。
きっかけはこのブコメである。
それに対しての記事がこれ。
id:honeshabriさんにすすめられた本読んでがっかりしてるなりよ。すごく楽しみに読み始めたけど侵略者の既得権益側にいる子育て嫌いな男が既存の価値観に自然をすりあわせて書いたみたいな本でげんなりしてるわ。「雄雌は子育てを相手に押し付け合っている」とか「押し切られた方が」とか半陰陽のことを「本物の女より女に見える」とか、いろいろひどくて見てらんない。
id:honeshabriさんがどういうお考えでこの本を紹介してくださったのかいつか教えていただきたい。
記事を読んで俺は思った。これは講義の必要があるな、と。誤字ではない。進化論と人類について講義するべきだと思ったのだ。
この人は明らかに進化論を誤解しているし、人類の祖先に対する認識もズレている。これは、ある種の思想を通して生命の進化と向き合ったがゆえに、本の内容を読み取ることに失敗したのだろう。
だがそれでも俺は文句を言う気は無い。
なぜなら、人は失敗する生き物であり、大切なのはそこから何かを学ぶということなのだから。
本を薦めたわけ
なぜ俺が『人間の性はなぜ奇妙に進化したのか』を薦めたのかというと、俺からしてみればこの本と『GO WILD』や『BORN TO RUN』は同じカテゴリだからだ。3冊とも、人類が進化の過程で獲得した形質が、現代の生活に影響を及ぼしている、という点に置いて同じである。さらにブコメ先の記事のテーマ「人類は本来ポリアモミー(乱婚型)であるか」についての回答が書いてあるからだから、薦めるのは当然であろう。
さらにこんなことも言っていたわけであるし。
さて、「同じカテゴリ」とは言いつつも、こと人類の進化についてのみ語るのであれば、俺は『人間の性はなぜ奇妙に進化したのか』のほうがより説得力があると思っている。それは他二冊よりも遺伝の効率について重要視し、その証拠を提示しているからだ。しかし、いきなり俺が擁護したところで聞く耳を持たないだろう。こんなことを書いているのだから。
ジャレドは自分の遺伝子を残すことを最優先に生命は進化したと考えているけれど、これは自然から出た結論じゃなく、相続を血縁に限定する欧米の社会制度を本能によるものだと考えた結果だとわたしは思うわ。
ポリアモリーとカップリングと集団保育と多読書感想文 - はてこはときどき外に出る
なのでまず進化における、遺伝子を残すことの重要性から説明していきたいと思う。
進化論入門
id:kutabirehatekoは、生命は遺伝子を残すことを最優先に進化したと考えるのは間違いであり、「自分の遺伝子を残す以外のミッション」があると言う。その根拠の一つとして他人の子供がかわいいから、と述べている。
わたしがこんな風に思うのは継母の連れ子である継妹の子、つまり血の繋がりのない甥介がめちゃめちゃかわいいからでもある。
ところが血の繋がりが何もない甥介が発狂するくらいかわいいのでわたしの中の「かわいい=血の繋がり説」は崩れ去った。コロニーの中で慈しんで育てる子はかわいいのだ。
ポリアモリーとカップリングと集団保育と多読書感想文 - はてこはときどき外に出る
あえて言おう。「かわいい」それは進化論にとって大切なことだろうか。
否、そのような要素は生物の進化にとって些細な事であり、基本原理には全く必要ない。生命の進化にとって大切なことは次の三つ。変異・遺伝・適応度である。これを理解せずに「多様性が必要」だとか、「猫の学習」だとかで進化を語るのは無意味だ。ポケモンで例えるならばHPも知らずに「役割破壊」や「130族抜き調整」を語るようなものである。というわけでこれら三つの要素の解説をしよう。
変異・遺伝・適応度
まず変異であるが、これは生命の持つ形質が変化することを指す。生命が多様性を持つのは変異が起きるからだ。そして変異が起きることによって、同じ種でも姿や行動に差が生まれることがある。この時、変異の内容についてはランダムであり、それが生存に有利であるとは限らない。有利なこともあれば、不利なこともあり、全く意味が無いかもしれない。変異はただ起きるだけなのだ。
二つ目の要素である遺伝、これは「遺伝」という単語から想像するまんまの意味である。つまり、親が持つ形質は子に伝わるということだ。無性生殖ならば変異が起きないかぎり全ての形質が伝わる。もちろん、変異が起きた生命が子を産めば、その変異で獲得した形質は遺伝によって子も持つことになる。
そして最後に適応度である。これは個体が他と比べて、一生涯にどれだけ子を残せるか、という値である。例えば普通サイズのクチバシを持つ鳥が1個体あたり平均2羽の雛を残せるのに対し、大型のクチバシを持つ鳥は1個体あたり平均3羽の雛を残せるとする。この場合、普通サイズの方を基準とするならば、普通サイズの適応度を1とし、大型の適応度を1.5とする。適応度は実際に結果として残した子の数で決まるのではなく、ある形質を持つ個体ならばどれくらい残せるかという、統計的に想定できる期待値となる。つまり、適応度が高い個体ほど多くの子を残せるのである。
これら3つの要素が組み合わさるとどうなるか。自然淘汰によって生命が進化する。
ここでダーウィンがいう自然淘汰とは、㈠動植物の解剖学的な適応形質には変異があり、㈡そのうちある適応形質をそなえた個体はその他の個体よりも長く生存し、多くの子孫を残すことができ、㈢それゆえこれらの適応形質は世代が進むにつれて集団のなかに広まっていくという意味だ。
文庫 人間の性はなぜ奇妙に進化したのか (草思社文庫)
実をいうとあの本にちゃんと書いてある。おそらくid:kutabirehatekoは深く考えずに読み飛ばしたのだろう。上記文章を正しく読み取れれば、ジャレド・ダイアモンドがあれほど「どうしたら遺伝子を残せるか」にこだわる*1理由も分かるはずだ。
とはいえ文章だけでは実感が沸かないと思うので、自然淘汰による生命の進化を単純なモデルで視覚化する。使うソフトはもちろんExcelだ。マスのことを「cell(細胞)」と呼ぶことからも分かるように、Excelはもともと細胞分裂をシミュレーションするために開発された*2。今回の目的にピッタリだ。
視覚化してみた
まず前提を説明する。
- 青と赤の二つの種が存在する (変異)
- 青からは青が生まれ、赤は赤が生まれる (遺伝)
- 青の適応度は 1.0 であり、赤の適応度は 1.1 である
- 開始時の個体数の比は 1:1 である
ここでは両者の差は純粋に適応度のみである。この際、なぜ適応度が異なるかはどうでもいい。青は自分の子だけを育てるのに対し、赤は共同保育をしている、でもいい。各々が好きな様に想定していればいいのだ。ここはとりあえず、青は喫煙していて、赤は禁煙しているとする*3。その結果がこれである。
横軸が世代交代数で縦軸が割合である。瞬く間に喫煙者が駆逐されていくのが分かるだろう。最初は同数であったのに、40サイクルもしたら2%程度になってしまった。自然淘汰が起きたのだ。
このように適応度が高いと爆発的に増えるのは、そこに複利の力が働くからである。生命の本質は自らを複製することだ。そしてその複製からもまた複製がされる。アインシュタインが言ったとされる*4言葉に「複利は宇宙で最も強大な力である*5」というのがあるが、こと生命について語るなら同意だ。
ところで、注意深い人はグラフの右上に緑があるのに気がついただろう。実は41サイクル目に変異で新たな種が誕生したのだ。この緑の適応度は 1.2 である。きっとコイツは酒を飲まないタイプなのだろう。酒は理性を失わせるし健康にも悪い*6。その結果がこれだ。
一度は支配者の地位を確立したかに思えた飲酒者も、緑が現れた途端にその数を減らすことになった。こいつらはしぶといが、もう50サイクルもしたら素敵な世界になるだろう。ところで右上に紫が。
コーヒーは精神を覚醒させる。
こうして紫が支配者となったのである。この一連の流れを、生物学者になったつもりで説明してみるとどうなるか。
「より多くの遺伝子を残すため、禁煙・禁酒を行い、コーヒーを飲むようになった」
しかし真実はそうでないことを諸君らは知っている。実際はこう言うべきなのだ。
「増える形質を持った種(遺伝子)が増える」
そう、生命は他の種との競争に勝とうしているのでもなければ、利己的に振る舞おうとしているのでもない。さらに進化には目指すべき場所も無ければ、ミッションも無い。ただ変異・遺伝・適応度という三つの要素によって形質を変えながら増えていくだけなのである。
やっぱり遺伝子を残したい
言うまでもなく、上記の内容は生物学者ならば誰でも理解していることである。反対の立場であろうとも、理解した上での反対だ。では生物学者たちは、なぜ「より多くの遺伝子を残すため〜」なんて言うのだろうか。答えは、その方が説明しやすいからである。
ここでもう一度、生物学者になったつもりの説明を見てみよう。
「より多くの遺伝子を残すため、禁煙・禁酒を行い、コーヒーを飲むようになった」
これでも結果としては正しい説明となっている。「禁煙・禁酒を行い、コーヒーを飲む」というこの流れは、より多くの遺伝子を残すことに繋がるからだ。そして「遺伝子を残すため」という目的は、どうしてそのような形質となったのかの説明に使える。「なぜコーヒーを飲むようになったかって?より多くの遺伝子を残すためさ」というように。
本来、因果関係は逆なのだが、説明にはこの方がいい。なぜなら「なんでコーヒーを飲むと遺伝子を多く残せるのか」というさらなる質問に対して「コーヒーは精神を覚醒させるから」と答えられるからだ。
したがって「より多くの遺伝子を残す」という事を目的として進化を語るのは理に適っているのである。実際はそのような目的は無かったとしても、結果としては「より多くの遺伝子を残す」ことになるのだから。
適応度高い系
ここまで来たらジャレド・ダイアモンドが「雄雌は子育てを相手に押し付け合っている」とか「カップル以外の雄雌が交尾をすることを雄にとってのダメージ」と書く理由も分かるだろう。そう書くことで説明できるからだ。もちろんその個体にとって実際にマイナス、というわけではない。ただ遺伝子が残らないだけだ。
もし自分が子育てをしないことでより多くの遺伝子を残せる=適応度が高まるのであれば、子育てをしない形質が広まっていく。中には変異で子育てを積極的にする、模範的なマイホーム個体も出てくるのだろう。しかし、それによって適応度が下がるのであれば、その形質は広まること無く消えていく。寝取られについても同じことだ。許容する個体の遺伝子は残らない一方で、寝取られNGの遺伝子が残るのであれば、やがてNGの個体だらけとなる。
そのようなわけで、生命が誕生してからの35億年間、生命は常に遺伝子が多く残せる方を選択してきた*7。もちろん実態は遺伝子を残せた方が残っているのである。だから進化の説明をする時は、常に遺伝子を残すためにはどうしたら、と語っていくのだ。
人類の歩み
進化論の基礎について語り終えたので、ようやく人類の進化について語る時が来た。
さて、例の記事では「人間を種としてカップリングするポリアモリーだろうと思う」ということで、その後理由が5個書いてある。
これを整理する。
- 狩猟採集時代を想定 (持久狩猟から論を展開しているので200万~100万年前)
- 人類はポリアモリー (乱婚型)だった
- 狩りは男女混合で男女平等な社会
- 集団生活による共同保育
- 血縁・遺伝子の軽視
ではこれらが妥当と言えるのか考えていこう。
昔は乱婚していたのか
きっかけのテーマでもあるこれ。現在の人類は一夫一妻制であるが、その昔はどうであったのか。「昔」をどこまで遡るかによるが、ゴリラやチンパンジーの祖先らと分岐した後ならNOだろう。これはジャレド・ダイアモンドの主張だけで十分だ。まず人間がゴリラやチンパンジーと分かれる前は一夫多妻制である。
今日のヒトと、ヒトに最も近縁なチンパンジー、そしてゴリラを見ると、三種類の配偶システムのすべてを見ることができる。ゴリラはハーレム、チンパンジーは乱婚、そしてヒトは一夫一妻とハーレムの両方をとっている(図4‐2参照)。それゆえ、九〇〇万年前の「失われた環」の三種の子孫のなかで、少なくとも二種はもともとの交配システムを変化させてきたのに違いない。これとは別に、「失われた環」はハーレム型だったと考えられる有力な証拠がある。
文庫 人間の性はなぜ奇妙に進化したのか (草思社文庫)
そして一夫多妻制の中で生まれた排卵隠蔽システムにより一夫一妻制に進むインセンティブが生まれる。
まず、排卵の隠蔽は乱婚かハーレム型の種のなかで生じる。次に、排卵の隠蔽が定着したところで、その種は一夫一妻に切り替わるのである(図4‐4参照)。
文庫 人間の性はなぜ奇妙に進化したのか (草思社文庫)
乱婚制の入る隙間は無い。
一方でid:kutabirehatekoの根拠を見てみると、全て社会システムだけで語っている。このような社会であったら乱婚になるであろう、と。これは19世紀に流行った社会進化論の主張と同じである。所有権の概念によって結婚制度が変わっていくというものだ。
もしそうであるならば、現在の狩猟採集民族も乱婚制度でなければおかしい。しかし、ほとんど狩猟採集民族は一夫一妻制か一夫多妻制で乱婚制はほとんど無い。まれに乱婚制に近いものがあったとしても、そこには条件がつく。
中央アフリカザイール北東のバンプティー・ピグミーの場合、かつては乱婚制であったらしい。しかし、女性の性的価値が上昇すると共に男性の権威が低下して弱体化。結果、滅亡の危機に瀕して女性の役割を性役から重労働にシフトさせた。そして婚姻形態は一夫多妻制、一夫一妻制へと移っていった。
タヒチ島の場合だと女性は12~13歳頃から性交のテクニックを教わり、奔放なセックスを楽しむ。これは外交にセックスを使うことがきっかけで、これが習慣化。ついには他部族や異国の来訪者にも性的歓迎を迎えるようになったという。
ニューギニアのトロブリアンド島の場合はかなり自由だ。性交渉に一切の束縛が無いため、幼いころから性的遊戯にふける。そして思春期になればいよいよもって乱交だ。これが成り立つのは、ここの島民は性交と妊娠の因果関係を認識しておらず、女だけで子供ができると思っているからである。ただし、結婚すると性交は排他的となり、決まった相手と行うようになるとのこと。
せいぜいちょうどよさ気なのはカナダ北西部に住むヘヤー・インディアンくらいだろうか。この部族は婚前は頻繁に、結婚後も複数の相手と性交渉をし、その上夫婦関係に永続性が無い。しかも多くのものは共同的というのだから、かなり社会進化論者向けではないだろうか。しかしこの部族では人に食べられて死ぬのは良いこととされ、自分の子供を罪の意識もなく食べたという記録がある。だからと言って人類の祖先は子供を食べるのは普通だったと考えるのはおかしいだろう。
以上の各部族の説明はここから持ってきた。
『婚姻論 』付 世界の各部族(PDF)
文化が違いすぎるので、どこまで正しいのか俺には判断できない。
というわけで人類は元々乱婚制であった、とするのは無理がある。もちろんそんな部族は存在しなかったと断言するつもりはない。だが基本は一夫多妻制からの一夫一妻制だ。それを覆す証拠はまだ出てきていない。
人類は採集者で、菜食動物
次は狩猟について意見を述べよう。はっきり言えば『GO WILD』も『BORN TO RUN』も狩猟を過大評価している。
人類は狩猟者で、肉食動物だ。菜食主義の社会があったという記録はどこにもない。肉を食べることが人類を定義づける基本的事実であり、本来の食性なのだ。
GO WILD 野生の体を取り戻せ! ―科学が教えるトレイルラン、低炭水化物食、マインドフルネス
人類はここで書かれているほど狩猟していないし、肉食か菜食かと言ったら菜食である。特に「ランニングマン」であるホモ・エレクトスの時代ならなおさらだ。まずはゴリラやチンパンジーと分かれた頃から説明していこう。
聖書で最初に人が食していたのは果実であったが、これは割りといいところを突いている。人類と近い存在であるゴリラやチンパンジーがまず果実を求めることから分かるように、人類の祖先も果実食であった。これは歯の摩耗の特徴から示唆されている。
アダムとイヴは禁断の果実を食したことで楽園を追放されたのに対し、初期人類は気候の変化で果実を食せなくなったことで、楽園からサバンナへ出るはめとなった。この時人類が食べていたのは塊茎、種子、植物の茎といったものである。地面の下からそういった地下貯蔵器官を掘り起こしていたのだ。
400万年前から300万年前にアフリカ東部に暮らしていたアウストラロピテクス・アファレンシスには、まさにその特徴が伺える。彼らは大きな犬歯を手放すことで臼歯を進化させた。類人猿と比較すると、それは歯というにはあまりにも大きすぎた。大きく、分厚く、平ら、そして厚いエナメル質*8で覆われていた。それは硬質な食物を噛むためである。もちろん顎も頑丈だ。もし俺がアウストラロピテクスならば、アイコンの下顎をもっと大きくしただろう*9。
およそ250万年前に石器が登場する。この時代の主役アウストラロピテクス・ガルヒでやっとまともに肉を食べ始める。しかしまだ脳のサイズが類人猿とそう変わらず、ランナーとしても完成していないガルヒに狩猟は無理だ。彼らは腐肉を漁り、石器で骨を砕き、中の骨髄をすすったのである*10。そしてまだまだ菜食がメインなのも変わらない。石器の大半は植物を切るのに使われていたからだ。
200万年前、ようやく「ランニングマン」であるホモ・エレクトスが登場する。彼らの走力はまず腐肉漁りに使われ、それから得たカロリーで脳を大きくする。そしてついに「持久狩猟」が行えるようになった。これでようやく男性は狩猟 (と引き続き腐肉漁り) を行い始め、女性は植物採集と、現代にも通じる狩猟採集民族の形ができ始めた。
男性が狩猟で女性が採集!
いったいこんな不届きで前時代的*11なことを言うのは誰なのか。
「持久狩猟」提案者の一人、ダニエル E リーバーマンその人である。
したがって肉食の発祥は、女性がもっぱら食料採集に専念する一方で、男性が採集に加えて狩猟と腐肉漁りも行なうという分業が確立したのと同時期だったと推測できる。
初期ホモ属が暮らしていたアフリカの生息環境では、間違いなく採集した植物が食事の大半だった。おそらくは七〇パーセント以上ではないか。
人体六〇〇万年史 上──科学が明かす進化・健康・疾病 (早川書房)
さらに彼はこんなことも書いている。
ところが狩猟採集民は結婚し、夫が妻と子に食料を供給するというかたちで多大な投資をする。現代の狩猟採集民の男性は、狩猟によって一日三〇〇〇キロカロリーから六〇〇〇キロカロリーを手中にできる。自分と家族の分を除いてもなお余るほどだ。大きな獲物をしとめたときは、その肉を仲間全員に分け与えるが、それでも最大の取り分は家族に与える(14)。
人体六〇〇万年史 上──科学が明かす進化・健康・疾病 (早川書房)
集団での分配、というのは確かに狩猟採集民族では必須である。しかしそれでも一夫一妻制にメリットはあるのだ。仲間は大切であるが、一番大切なのは自分の遺伝子を受け継いだ子供なのだから。
ジャレド・ダイアモンドだけでなく、ダニエル E リーバーマンですらこう言っているのだから、これが基本形ということなのだろう。もちろんこれも例によって、女性が狩りに参加することは 0 であった、と言うつもりはない。ただ一般的には狩猟採集民族であろうとも男女の分業はあったと考えたほうがいい。そして、血の繋がりを優先することも。
まず思想を捨てよ
以上で反論は十分だと思う。書いている方も疲れているのだから、読んでいてうんざりしている人もいるだろう。だがまだ終わりじゃない。
今回、id:kutabirehatekoが『GO WILD』と『BORN TO RUN』を高く評価し、『人間の性はなぜ奇妙に進化したのか』を強く否定したのは、カエサルが言ったとされるこの言葉に尽きると思う。
「人間ならば誰にでも、現実のすべてが見えるわけではない。多くの人は、見たいと欲する現実しか見ない」*12
彼女のブログ「はてこはときどき外に出る」を読んでいると、ある思想が前面に押し出されているように思える。それは性役割を押し付けられることへの拒否と血縁を重要視することの嫌悪である*13。
「女子力」とは言い換えると「嫁力」で、「未熟な若い娘が好むと思われていること」「嫁にもらってもらえそうなこと」の代名詞になっている。そこにあるのは男性に選ばれるにふさわしいとされる古典的な女性の鋳型であって、女子が自分独自の力に自信を持つことを後押しするようなものではない。
女性のエンパワメントとハイヒール、そして男子とネクタイ - はてこはときどき外に出る
そもそも苦しいとき、辛いとき、困ったとき、寂しく心細いとき、血の繋がりによって強められるだろうか。どう考えてもそうではない。血の繋がりは魔法のように受容や慰撫をもたらしてはくれない。
おかあさんがほしい。おかあさんになりたい。 - はてこはときどき外に出る
この視点で例の3冊を見てみると、はっきり二つに分けられる。そのため俺にとっては同じカテゴリであっても、彼女にとってはそうでなかったのだろう。
別に俺は他人の思想にとやかく言うつもりはない。国や時代によって価値観が異なるのと同様に、個人間でも異なるのが当たり前だからだ。それにどちらかと言えば俺も性役割とかどうでもいいと思っているし*14、血縁よりも関係の深さが重要だと思っている*15。だが進化論を含め、科学に向き合うのであれば違う。誤解を恐れずに言えば、科学に対する時は思想を捨てるべきだ。必要なのは仮説である。
これは科学の歴史を見ていれば分かる。万物は数であると信じたピタゴラス学派は無理数を見なかったことにした。キリスト教徒のチェーザレ・クレモニーニは「天空にはふつうの計測の規則は適用されない」とガリレオ・ガリレイを批判した。余計な思想があると、見えるべきものも見えなくなるのである。
生物学においても同じようなことは起きている。現代の日本でも時折言われる「自然界には同性愛が無い」というものだ。もちろんこれは間違っている。前世紀には分かっていることだ。
それでも同性愛を不自然だと信じたい人の目には入らない。
今回の件も、俺からしてみればこれらと大差ない。
科学と向き合うならば、自分の思想を捨てる必要があるのだ。
次に読むべき本
「終わりに」に代えてid:kutabirehatekoが次に読んだほうがいい本を紹介しよう。もしすでに読んでいるならば読み返すべき。
進化論の入門書としてお勧め。薄い本なのですぐに読めるのがいい。筆者曰く「日本人ならばウィルソンの本を買ってはいけない。日本人向けに書かれたこの本を買うべき」とのこと。
記事中でも紹介した「持久狩猟」提案者の一人、ダニエル E リーバーマンの本。「ランニングマン」がどのような種であったのかこれで分かる。
人類の進化とは全く関係ない本。人の行動はインセンティブで決まるということが分かる。たぶんこの手のドライな本を読んで耐性をつけた方がいい。
進化論を学んでからもう一度挑戦すべき。
参考文献
目的別な本の紹介記事



























![[まとめ買い] プロレススーパースター列伝 [まとめ買い] プロレススーパースター列伝](http://ecx.images-amazon.com/images/I/E1PXy-wZouS._SL160_.png)





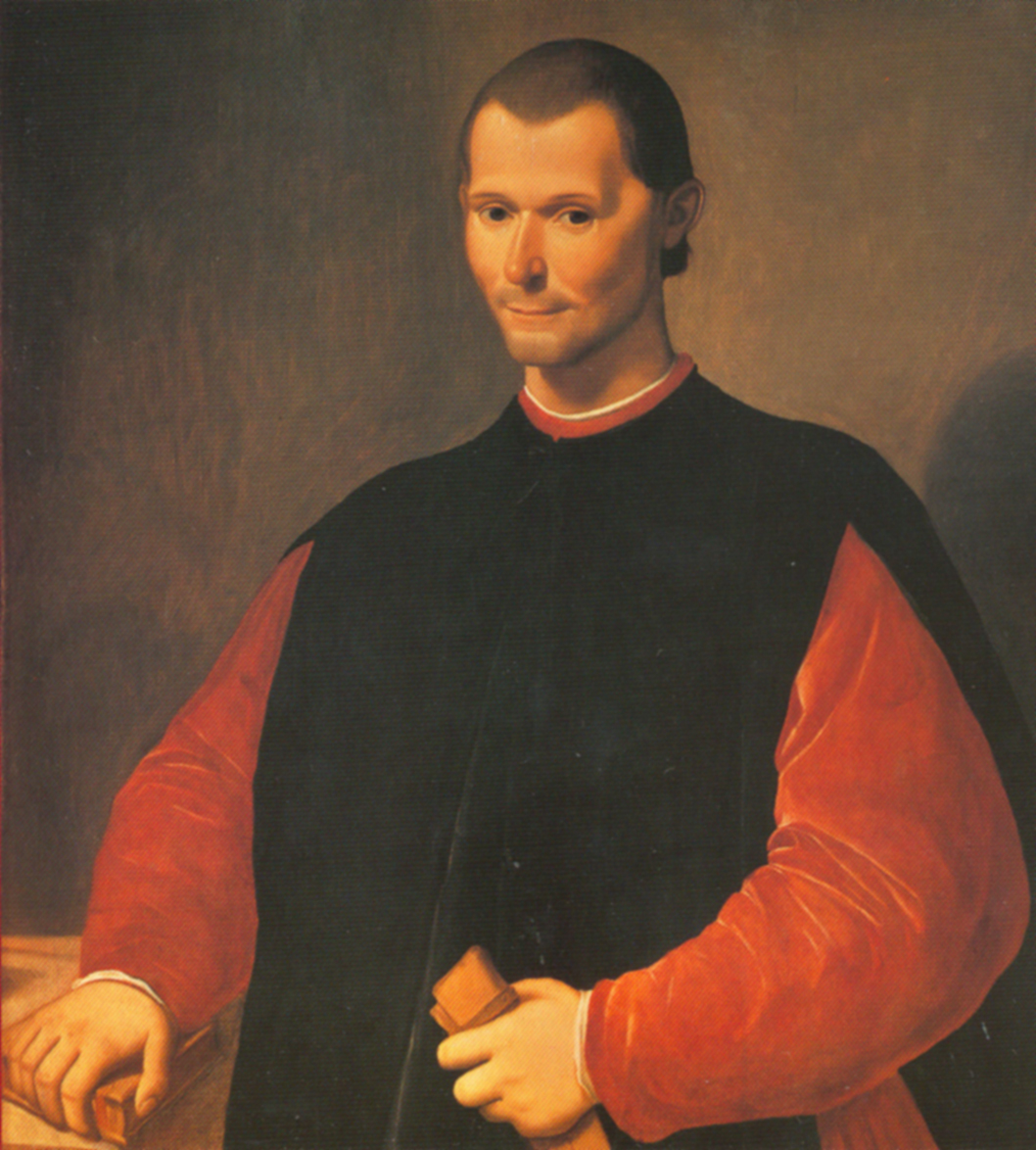






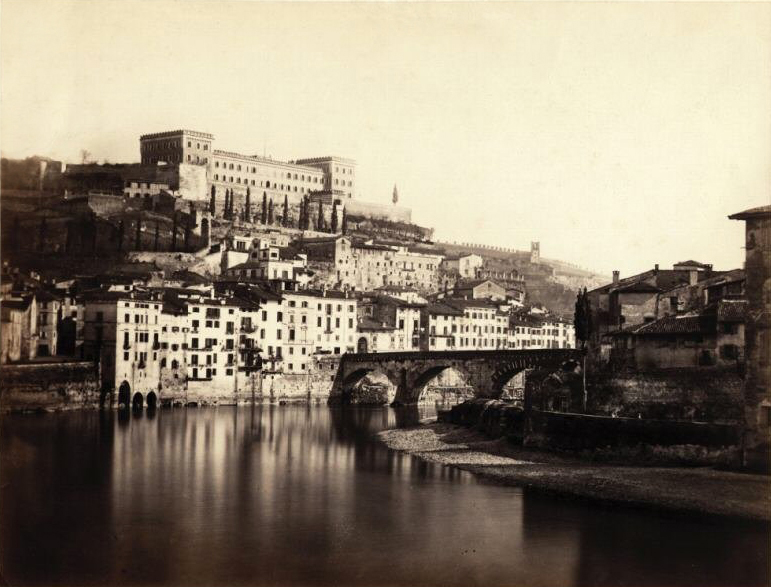


























![ヤバい経済学 [増補改訂版] ヤバい経済学 [増補改訂版]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51akOFFAMBL._SL160_.jpg)



























![MAGFORCE マグフォース MF-0315 M-5 Waistpack TAN free [ウェア&シューズ] MAGFORCE マグフォース MF-0315 M-5 Waistpack TAN free [ウェア&シューズ]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61hGM%2B1Sg4L._SL160_.jpg)


















![あまえないでよっ!!喝!! VOL.1(初回版・CD同梱) [DVD] あまえないでよっ!!喝!! VOL.1(初回版・CD同梱) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31JVWG6YAPL._SL160_.jpg)
















